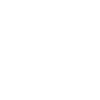7月15日は「お盆」です。「お盆」と言うのは、梵語の「ウランバナ」を「盂蘭盆(うらぼん)」と書いたところから来ています。もともとは“甚だしい苦しみ”という意味です。それが地獄で餓鬼道に落ちて食べることもできず、痩せ衰えているご先祖さまに食べものを供えて供養し、その冥福を祈るという行事になりました。中国では「倒懸」と訳しました。「倒懸」というのは「逆さ吊るしになる苦しみ」ということで、この苦しみから先祖を救うために供養をします。民族の伝統として「お盆」をするわけですが、そうするとお盆を守るというのは、自分のご先祖さまはとても天国には行けない悪い人たちで、みんな地獄で苦しみ悶えていることになります。それで子孫たちがお供えをして、その供養に励むことになります。よく先祖の供養が足らないなどと脅し、金品を巻き上げる「詐欺」がありますが、原因はこの「お盆」の信心があるからではないでしょうか。
聖書には以下のような御言葉があります。
「そして、霊においてキリストは、捕らわれていた霊たちのところへ行って宣教されました。この霊たちは、ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられたのに従わなかった者です。」
ペトロの手紙一3章19~20節
「ノアの箱舟」に乗らないで、洪水に呑まれてしまった人々のところにも、主イエスは十字架の後に黄泉にまで降って救いの福音を宣べ伝えられました。キリスト教は罰する教えではなく、どこまでも平和と救いのメッセージです。 V 園長 長村亮介